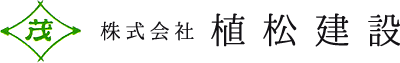<罰>は<罪>を抑止できるか?その4
人が乳幼児期に肉親から受けた心の傷は、成長して時に<罪>を生む「悪の芽」になる。
だが、心の中にある「悪の芽」が、当然ながら必ずしも<罪>を犯す行為として出現するわけではない。
ある時期の<経験>を通じて、成長が止まる「芽」もあれば、また成長を続ける「芽」もあるだろう。
社会というルールの中で、心の中の「悪の芽」をコントーロールしながら生活を重ね、死んでいく人が大部分と思う。
心の中にある「悪の芽」に気付くことなく、平穏に暮らし死んでいく人の方が多いのかもしれない。
文学などを志さなければ、自分のこころの「悪の芽」を見つめる必要もない。
病気と一緒で、「芽」が<罪>として発症しないまま死んでいければそれに越したことはない。
「悪の芽」が他者を害する方向に向かわず、自らを害する側に出現し、
自分の存在を自ら毀損し続け、破滅的な人生を生きるひとがいる。
少年期、『無頼派』と呼ばれた太宰治、坂口安吾、織田作之助、田中英光、檀一雄などの作品に浸っていた時期、
何故彼らは自分の人生を毀損し続けるのかよく理解できず、ただただ多感な少年期には恐怖があった。
今では多少なりと彼らの苦悩やその時代的契機、その反映の結果としての作品に多少なり理解が及ぶようになったが。
以前若い女性が「自傷行為」を繰り返す映像を見たことがある。
日常に突然侵入した非日常の映像は、痛ましくて見てはいられなかった。
自分(心)を持て余している姿からは、幼少期に受けた何らかの心の傷が発芽し、自傷行為を繰り返させると思えた。
自分の身体を傷つけて、誰に何を伝えたいのか?
おそらく、最も身近な父や母へ若しくは恋人への愛の渇きを叫んでいるのだろう。
人が心の中に持つ「悪の芽」若しくは「心の傷」に対し、私たちはどのように向き合えばいいのだろう。
日本を代表する文学者、太宰治と三島由紀夫は、人が心の中に持つ「悪の芽」若しくは「心の傷」に向き合う姿を、
その作品と生き様で私たちに示している。
どちらも最後を自死という形で締めくくった作家だが(田中英光も自死)、かれらの対極的生き方は、
それぞれが持ってしまった深い傷とのすさまじい格闘を教えている。
二人に共通する悲劇は天才ゆえの悲劇だろう。
彼らの自死という選択も、それぞれ周到に準備された「劇」のようだ。
「選ばれてあることの恍惚と不安われにあり」と書いた太宰の「不安」と、
彼を嫌悪した三島の天才ゆえの「不安」は、
それぞれの長い格闘の末に、皮肉にも同じ形でエンディングを迎えた。
三島由紀夫は、生前太宰治を嫌悪していたようだ。
太宰の作品にみられる「弱さの吐露」を嫌悪し、太宰の作品に表れる弱さを
「乾布摩擦で克服できる程度のもの」と書いた文を読んだ記憶がある。
三島の太宰への嫌悪感を、「近親憎悪」と評した批評も読んだ記憶があるが、
虚弱な体質と、容姿へのコンプレックス、鋭敏過ぎる感受性、お坊ちゃま育ちなど二人の相似点は多い。
三島由紀夫は、彼一流の研ぎ澄まされた嗅覚で、
太宰治の中に、三島自身の中にある「好きになれない自分の姿」を見たのだろうか。
二人の作家は、生まれてすぐに生母から無理やり引き離され、祖母や乳母に育てられたという同じ経験を持っている。
人がその人生で一番母性の愛情を必要とする幼児期に、
母性の愛情から隔離されて育った人間の心のひずみは想像以上かもしれない。
二人を称して「こういう育ち方をしたら、まっとうに生きられない」(主旨)と語ったのは、吉本隆明だったと思う。
乳幼児期ほど人にとって愛情が必要な時期はないのかもしれない。
『津軽』という作品の中で、太宰が自分の幼少期の子守だった「たけ」に会うため運動会に行くシーンがあり、
その喜びが横溢した文章に、シニカルな太宰らしくないと違和感を持った記憶がある。
このシーンは、研究者によると実際は「たけ」とは言葉も交わさず、作品にある「たけ」とのほのぼのとした会話もなく、
まったく太宰一流のフィクションらしい。(まったくこの作家は油断がならない!)
太宰の少し過剰に見えるこのはしゃぎ(実際はフィクション!)も、彼のこころの飢えを示していたのだろうか。
太宰や三島にとっては、幼児期の体験(母性の愛情の枯渇)がかれらの心に深い傷を生み、
それを見つめ克服するために文学を必要としたのかもしれない。
片方は過剰なまでに(けっこう嘘も交えて)自己の弱さを吐露し、一方はボディービルや武道、美学などで武装し、
それぞれ作品を世に送り出していく。
おそらく、文学という<糧>がなければ、二人共もっと早く自死を選択していたかもしれないし、
あるいは普通のエリートとしてよく見かける人生を送ったかもしれない。
二人は、余人からは「理解の空白」が残る自死をした。
かれらの中で、自死する必然性があったのか、当事者以外誰も最後の部分は分からないが、
どうしても傍から見ると釈然としない部分(核)が残る。
親鸞を用いれば、『業縁』によって自らを死に導いたのだろうか。
かれらの傷は天与の才を持っても克服できないほど深かったのか、
それとも文学という選択をし、絶えず自らの心を覗き続けた故なのか(職業病?)、私にはわからない。
ただ二人の天才が、生まれてすぐ生母から引き離されたという傷に生涯拘束されたのは事実であろう。
かれらの心にこの深い傷がなければ、私たちは二人の天才的な作家を持つことはなかったかもしれない。
続く
焼き締め壺(荒土)