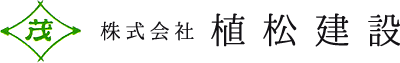老人文学または「風々居士」のエッセー
毎年のことながら3月年度末は仕事に追われ、週1回の休日も雑用と昼寝で終わってしまう。
「週休2日」の時代といっても、建設業の年度末は春先の降雨日があるから掛け声に過ぎない。
いつ頃から日本が週休2日制になったか忘れたが、
今もって私の思いはトリュフォーの名作『日曜日が待ち遠しい』の題名そのままだ。
こんな粋な題名が生まれた時代の方が、いまよりずっといい時代だった気がする。
何もしない日曜日もそれはそれで身体の休息にはなるが、そのままでは気分転換とはならず、頭から仕事を抜くために読書か陶芸になる。
しかし陶芸は、その最中はあまり感じないのだが終わった後の身体の疲れがひどい(要するにろくろが下手ということ)ので、
3月は身体に楽な「寝ながら読書」となる。
私の理想的な読書の姿は、陽だまりの中で数ページ読んでは少し昼寝をし、これを何度か繰り返すことだから読書とも言えないし、
私の読書はただ単に眠るための儀式で、例えば翌朝になると複数読んだ短編の題名を忘れていたり、
ストーリーを思い出すのに時間が掛かったりすることがある。
そんなことから、3月は中身を忘れても良いような軽いエッセーを中心に読むようにしているのだが、
3~4ページの文章にも作家の個性的な至言や思ってもみなかった発想などがあり、
睡眠薬代わりの読書も結構集中力が必要だ。
最近はそのまま読み流すには惜しいページに付箋を貼り、後日頭がしっかりした時などに読み返すようにし始めたが、
若い頃はそんなこともなかったから、長年使わなかった脳が人より早く老いはじめたのかもしれない。
今年の3月はずっと「風々居士」山田風太郎の晩年のエッセイ集が睡眠薬代わりになっている。
「老人文学」などと言うカテゴリーがある訳ではないが、老境に達した作家たちのエッセーを読んでいてふとそんな言葉を思いついた。
この場合殆どの作家は70過ぎの作家で、やはり彼らの関心が老いや死に向かっているから何かしら興味を惹かれる。
ひとが他人の死を通じて自分の死を考え始める時期が何時頃からか、当然個人差もあろうが、作家の場合70過ぎ位からが多いように思う。
彼らのエッセーを読むと、やがて来る自らの死に対し格別哲学的な、または宗教的な思索や見識を語っているわけでなく、
どちらかというと身に付いた文学的な視点から、いつか来るその日を淡々と思い描いているような文章が多い。
私自身はまだ死に向かって覚悟を決め、淡々と受け入れる準備をするには少し早いような気もするが、
生来自分の「先」にあるテーマについて書かれたものを読むのが好きだから、少し先であろう死をテーマにした文章は非常に面白い。
そんな中でも、一番ストレスのたまる年度末ということもあり、辿り着いたのが山田風太郎のエッセー集の再読だった。
この作家の一世を風靡した忍法物や伝奇もの、明治物など多彩な小説群は全く縁が無く、一作すら読んだこともないはずだが、
ひょうひょうとした題名に魅かれてエッセー集はずいぶんと読んだ。
エッセー集『あと千回の晩飯』、インタビュー集『いまわの際に言うべき一大事はなし』は確か単行本をもとめた記憶があり、
おそらく探せばどこかにあるはずだ。
寝ながら読むには単行本は大き過ぎるので、今ではどの作家の単行本でも殆ど買わなくなったが、この作家のものは単行本が多い。
山田風太郎のひょうひょうとした生き様は、エッセーよりもインタビューの方が格段にその「風々」ぶりが現れていて面白いが、
エッセーを読むと同じことを何度も繰り返して書き連ね、作家が言うとおりボケているのかと思わせるほどだが、
細かい箇所の記憶が非常に鮮明で、同じことを数回書いても少しの違いもないから不思議な頭脳だと思う。
作家に限らず、
ひとと長く付き合うには好き嫌い構わず全面的に入れ込むか、あるいはある部分だけに自制して限定的に付き合うかのどちらかかと思うが、
私にとってこの作家はエッセーとインタビューに限った方が面白そうだ。
作家は三日でウィスキー1本を開ける酒豪で、インタビューの際は殆ど酔っぱらった状態で話しているから、
文学表現の時のような推敲が当然無く、それ故読み手をニヤッとさせる本音が続く。
よく言われることだが、「何とか楽をして暮らしたいため、いろいろ苦労を重ねた」、「いやなことはしない」、「横着」な作家の「風々」ぶりは、
生き方として私には縁遠い分、とても格好良く見える。
作家には『戦中派不戦日記』という白眉の作品があり、戦時中の世の中の雰囲気を肌で知ることが出来る。
このころから作家は多分相当のメモ魔(日記魔)で、そのさまは年老いてからのエッセーでも十分にうかがい知ることが出来る。
作家の一日の終わりは日記を書くことかとも思うが、昨晩のおかずすら時に忘れる私とは脳の構造が全く違っていて、
自身が自分をよく「アル中ハイマー」と自虐するが、その記憶力は常人ではない。
おそらく一日一日を、初めて体験するような好奇心で過ごさなければ忘れてしまう小さな体験を、
どのように記憶の壺に入れるのか、肝心なことを書いた文にはまだお目に掛かっていない。
私が一番好きな作品は「人間臨終図巻』で、この本は何度読んでも読み出したら止められない。
800人ほどの歴史的な有名人を死亡年齢の若い順に並べ、臨終のさまを数行から2~3ページほどで簡潔にまとめ、
かつ作家の感想も交えて書いたものだが、簡潔である分、死者への親近感や死への親和性(?)が生まれてくる。
この作家のひとの死(臨終)に対する興味の深さが、これほどに膨大な数の臨終劇を書かせたと思うが、
「蒲柳の質」で自他ともに長生きは出来ないと言われ、死と隣り合わせに生きて来た人間ゆえの深い死への洞察があると思っている。
「眠られぬ夜の読書」としてはエッセー集と共に最良の一冊(文庫本は4部)だと思うが、
3月は疲労の極致にあるからあまり眠れないことはない。
↓黒釉壺
「逆さ卵」型の壺は好きで良く挽くが、
この形の壺ほど不人気なものはない。
思うに現代人にはこの形が見飽きた形になってしまっているのだろうか?
作り手の解放感の割には貰い手が少ない。
私自身は清水卯一のこの形の壺などいくら見ても見飽きないのだが・・。