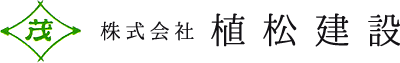ニッポン自殺考
学生時代の知人から共通の友人が自殺した、と電話があった。
彼の顔を思い浮かべたが、帰郷して以来会っていなかったので、若い頃の顔が思い浮かんだ。
彼と私の中では、お互い若い頃の記憶や風貌のまま時間が止まり、数十年が経っていたことが奇妙だった。
連絡を取り合わなかったのは、例えば歌人の歌のように
「傘なくばレインコートの襟立てて さよならだけの人生を行く」とか、「さらばばらばらあっけなく・・」
という感傷が私の方にあったからだ。
彼の方にも、詩人の詩のように「もたれあうことをきらった」矜持があったのかもしれない。
電話口で思わず「何故?」と聞いたが、すぐ愚問だと思った。
知人によれば、糖尿病と肝臓がもう手当のしようがない状態だったそうだが、
自死を選択した原因を推し測っても、自死を選ぶ最後の決断は誰にもわからない。
自分のこころを少しだけ納得させるため原因を尋ねたが、それとて無意味で、楽しくない連絡に対しつまらないことを聞いたと思った。
知人が残された家族にこれからの生活を尋ねたところ、「大丈夫との返事だった」のがせめてもの救いだ。
もっとも家族は大丈夫としか答えようもないだろう。
友人の自殺が、彼にとって何らかの解決になったことを祈るしかない。
学生時代、濃密な時間を共有した友人のうち、早くに死んだ奴は、
「無頼派」と呼ばれた一群の作家たちのように、まるで自分の身体を損なうことが生きる糧のように生きている、と私には見えた。
市井に生きる自分の姿に、彼ら自身が違和感を持ち続けたのだろうか。
しかし、社会にうまく融け込んで生きている奴(私も含めて)も、それぞれが何かの屈折を抱えて生きていると思う。
死を選択したものに対して、生きているものは何時だって「どのように生きても恥」(佐々木幸綱)だと思っている。
私は幸運にも、自死を考える場面に遭遇することなくこの歳まで生きて来た。
若い頃から進退窮まって逃げ出したい場面には何度か陥ったが、自死を考えることはなかった。
それが資質によるものなのか、生きて来た時間や環境の中で生まれた価値観によるのか、
それとも現実的には、自死を思うほどの苦悩や病気に出会わなかったのか、あまり突き詰めて考えたことはない。
ただ漠然とだが、何時かは死ぬのだから別段今でなくとも良かろう、という思いがあるだけだ。
厚労省のデーターによれば、日本では平成10年から23年まで年間3万人以上の人が自殺し、
24年以降は辛うじて3万人を下回って今日に至っている。
当然この数字の裏側には、自殺を図ったが死にきれず生き残ったひとや、瀕死の状態で病院に入りその後植物状態になったり、
ある程度の時間が経過して亡くなったというひとの数は入っていないと思われる。
真偽は不明だが、例えば医者が自殺と判断しない場合や遺書が無い場合は、自殺と見なされないとか、
死亡原因が明確に自殺と判断されない場合は「変死」として扱われ、「変死」と分類される死者の数は倍以上あるとか、
厚労省と警察庁で自殺の判断基準が異なるとか諸説あって、
それらを勘案すると、実際に自殺行為を行ったひとの数は、もっと圧倒的に多いと思う。
一口に3万人というが、私の住む市の隣に清水町という町があり、この町の人口が31,500人ほどだから、
数から考えれば、この国では毎年ひとつの町の住民全員が自殺し、3万人規模の町がひとつ消滅しているという勘定になる。
年間3万人の自殺者を実感として理解することは殆ど不可能だが、
近隣の市町の住人が1年で一挙に消滅する、と想像すると恐ろしい数字になる。
私には詩人・石原吉郎の影響だと思うが、死者を数で表すことに抵抗感がある。
数にした途端、個の時間を生き、個として死んだひとの尊厳や命を冒涜するような気がするからだ。
だから「一人の死は悲劇だが、百万人の死は統計上の数字に過ぎない」、と言ったアイヒマンやスターリンの発想を根絶しなければならないと思う。
何かに背を押され自死に赴いた人は、決して我々と別の時間や社会を生きていたのではないし、
3万の死には不本意に途絶された3万の固有の生があるのだから。
神奈川県座間市で、自殺願望のある学生などを自殺同伴者を装って殺した男のニュースの中で、
唯一私たちが救われるのは、9人の被害者全員が本当は自殺する気が無かった、と加害者が供述していた点だ。
死の想念に弄ばれながらも、根底のところで死を拒絶していたという被害者が語るものは、
9人の殺されたひとも何かの契機や対応によって、生きることが可能であったと教えている。
その対応は個別的で非常に複雑ではあろうが、政治や社会がもっと何らかの手を打てたはずだ。
自殺のニュースに接するたび、生と死の「境」が安直に越境されたのではないか、というやるせなさを感じるのは私だけでないはずだ。
政治が「少子化対策」などと声高に叫ぶ前に、生きている人間の命を救う方が余程重要なテーマだと思う。
日本社会の暗部にはいつも死の想念が漂い、それが何かの拍子に個人を死に誘うのかもしれない。
そう考えれば、自死を選ぶのは決して他人事でなく、明日の私達の姿と考えた方がいい。
死の想念に絡み捕られたひとの生と同じ時間や空間を私達も生きているのだから。
毎年3万人の人が事故や病気でなく、自ら死を選ぶ社会は病んだ共同性の極みだろうが、
なぜこの国の社会が強固な死の想念を隠し持っているのか、よく分析は出来ていない。
自殺者の多い国や地域というと漠たる知識ながら韓国が思い浮かぶ。
韓国の場合、高齢者の自殺率が高いと言われ、一般的には高齢になってからの生活や将来への不安が原因と言われる。
確かに「老い」の一番怖いところは、小さな不安を頭が勝手に増大させてしまい、
客観的な不安の測定が出来なくなる、と私自身が老いるにつれ切実に実感しているから、
高齢者が本当は乗り切れるだろう不安に押しつぶされてしまうのも、この齢になるとよく想像が及ぶ。
韓国にこうした傾向が顕著だとすると、韓国社会も日本と同じようにどこかに跛行の根源が隠されているような気がする。
韓国における儒教が、どの程度人々の不安や恐れを癒し、救済しているかよく分からないが、
日本の仏教と大差なく、社会が生み出す不安や恐怖に対し、先頭で防波堤になるべき宗教が全く無力であることは想像に難くない。
自殺は身体が死を求めるのでなく、心が死を求めて行為を引き寄せるのだから、
「病んだこころ」を受け止める宗教や理念(価値観)が求められているはずだ。
余談だが、仏教者の話を聞く機会が時々あるが、彼らの話は教義に対する知識(教養)は職業柄豊かだが、
その中身に現実に苦悩する人々への生きるヒントや励ましは殆ど感じることが無い。
私がそうしたつまらない宗教家にしかお目に掛かっていないだけかもしれないが・・。
現代社会の暗部に底流する不安や苦悩に対し、既存の仏教思想が無力である分、新興の宗教が心の不安を埋めるように派生するのかもしれない。
神や仏の「代理人」たる宗教家のていたらくは、別段いまに始まったことでもないから、
私たちは「ことにおいて神仏をたのまず」という矜持を持って生きるしかないのかもしれない。
自殺の原因として、病気(うつ病なども含む)、倒産や負債(私の場合を考えるとこれが背中を押すと思っている)、
生活苦、家庭や職場の人間関係など、ひとが生きていく社会で永遠に消滅しないだろう原因が考えられる。
ということは、どれほど豊かで住みやすい社会が出現しても、ひとが自らの手で自らを殺す行為はこの社会から消滅しないかもしれない。
だが、医学の進歩や社会の寛容性の拡大などが自殺を減少、防止することは可能なはずだ。
私が多少なり親しんだ文学者の自死も、当たり前だが核心がよく分からない。
太宰治、村上一郎、三島由紀夫、江藤淳の自死には半ばの納得と半ばの疑問がある。
三島由紀夫の割腹自殺の時、私は予備校生で、その晩は興奮状態で同級生と夜を徹してその死を話し合ったが、
実のところ、隔靴掻痒のようだった思い出が残っている。
今は、三島の自殺は「観念としての天皇制」に作家の描く美や文化を収斂させようと格闘した末の、諦念による自刎だったような気がする。
しかし他の文学者の自死も同じで、長い間の文学的営為の果てになぜ自死があるのか疑問が残ったままだ。
老いや病気、事故などの「向こう側から来る死」を待たず、「自分の意志で向かう死」を選んだ作家の判断は、
彼らの文学やその生き様と通底するものがあるのだろうか。
一番よく読んだ太宰の自殺には、このごろかろうじて私なりの稚拙な理解が生まれているが、
太宰よりも30年程長く生きて、少しだけ作家の戦後社会の中での立ち位置や苦悩が見えて来たからかもしれない。
ちなみに、太宰38歳、石川啄木26歳、宮澤賢治37歳、夏目漱石49歳で亡くなっている。
何故近代の文学者は、現在のわれわれと比べ、その成熟が別格に見えるのだろう。
↓不知火土に刷毛目の蹲
初めて白化粧土を使ってみた。白化粧土は貰いもの。
花が活けてあるからまあまあだが、花が無いとどうだろう。
それにしても、もう少し気を使って花を活ければよかったが、
それでも荒土の花生は花をよく引き立てると思う。