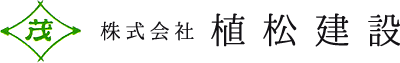国宝の青磁作品について(その2 青磁鳳凰耳花生)
「青磁鳳凰耳花生」と呼ばれる槌(つち)形の花生は、和泉市久保惣記念美術館が所有する国宝の銘・「萬声」を頂点に、
京都の陽明文庫蔵の重要文化財 銘・「千声」等数多くの優品が日本にある。
重文指定を受けたものは、他に大阪市立東洋陶磁美術館所蔵と五島美術館所蔵のものがあり、
根津美術館、常盤山文庫にも素晴らしい鳳凰耳の作品がある。
これらの作品は、おおむね南宋時代から元時代初期にかけて中国龍泉窯で焼かれ、鎌倉時代から室町時代にかけ日本に請来したとされ、
幾人かの権力者を経て、ほとんどが明治以降の近代国家建設の過程で巨万の富を得た財閥創始者の掌に渡っている。
「萬声」と「千声」はそれぞれ徳川家光から他所に移ったとされ、来歴が辿れるゆえに国宝、重文の指定を受けているが、
「青瓷鳳凰耳花生」はどれもが日本の歴史の中で、いわば権力を象徴する作品として位置してきたやきものと言えよう。
「権力の象徴」という歴史的役割を担ったこれらの作品は、中国から請来した他の青磁作品群においても屹立し、
いまも 見る者を圧倒するオーラを放っている。
これらの作品の高さはほぼ一定で、公表されたデーターによると
「萬声」は33.6cm、「千声」33.5cm、五島美術館の作品が33.5cm、東洋陶磁28.8cm、常盤山27.6cmとある。
おおむね公開されている鳳凰耳は33cm強から27cmの範囲に分布しているようだが、
まだ私がお目に掛かっていない本歌の鳳凰耳も当然あるかもしれない。
以前左右の鳳凰には雌雄があると聞いたことがあるが、事実かどうかは不明だ。
学術的に見ると、浙江省龍泉窯で作られたこの手の作品は、おそらく日本以外にも多くが輸出されたはずだが、
中国をはじめベトナム、タイ等他の東南アジアの国には日本にあるような優品が無いと言う。
加えて、他の作品(青磁鯱耳花生、青磁鯉耳花生)の陶片は国内で出土した例はあるが、
鳳凰耳の陶片についての出土事例はないという。(陶説757号より)
「青磁鳳凰耳花生」はいまだ多くの謎に包まれた作品といえるが、
日本人は南宋時代のこの釉色を「砧青磁」と名付けて青磁作品の頂点に置き、多くの人々が魅了されてきた。
中国陶磁に関心のある作家たちは、殆ど誰もが一度はこの鳳凰耳に挑戦し、今も多くの作家作品が残っているが、
作家の個性を表現する(加える)余地のないこの作品は、
忠実にその姿や釉調を写すくらいしか関与できないほど完成された形といえる。
陶聖・板谷波山にも鳳凰耳花生があり、妥協を許さぬ波山らしい緊張感のある作品だが、
胴部に連弁文を施し、 胴と首のバランスを変え、それでも違和感のないバランスを保っているが、
近代陶芸の頂点・波山をしても、 この形においてはそれ以上の個性を加えることは不可能だったようだ。
波山の鳳凰耳の釉調は所謂「砧系」でなく「天龍寺系」に近い。
『web悠果堂美術館』のトップページにも「青磁鳳凰耳花生」が掲載してあるが、
この作品はおそらく日本にある鳳凰耳の中で最も小さな作品だと思う。
高さ15.5cmで不思議なことに胴部に「ツナギ」を設けてある。
ツナギの技法は一般的には胴と首の境に設けるか、首の中間に設けるのが「常識」だが、
この作品は考えられないことだが胴部の下で繋いである。
青磁鳳凰耳花生の不思議なところは、首の両側の鳳凰耳を取ってしまう(写真の場合指や紙片で隠してみる)と、
まったくバランスの悪い砧形の瓶になる。
ところが二つの耳が付くことで、これ以上変えようのない完成形になるというのも驚き以外のなにものでもない。
文化の豊かな宋の時代の美意識の高さに、現代の私たちはまだ及ばないかもしれない。
鳳凰という空想の鳥を耳というパーツにしてしまう宋時代の豊かさは、元時代になると歴史的に変質、消滅してしまい、
「天龍寺青磁」と呼ばれる緑系の釉調に変わっていく。
↓青磁鳳凰耳花生(南宋後期の作かと思う)
胴部の中間で繋いだ跡が分かると思うが、
中国古陶磁に精通した若尾先生も首をかしげる位置での繋ぎだ。
この作品は両耳を隠しても多少のバランスは取れるが、「萬声」「千声」にいたっては、
耳を取るとまったくブザマな形になる。
釉薬は想像するほど厚くなく、胎土は現代の青瓷作品に典型的な鉄分たっぷりの土ではない。
灰色の半磁器土のような色合いだ。
釉薬が薄くてこれほどの調子が出ることが何より不思議だ。