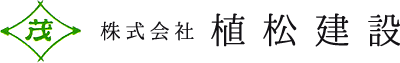無名のまま
「棺の蓋が閉まる時まで人の評価は定まらない」(棺を蓋いて事定まる)というが、長い時を経て生前無名だった評価が突然沸騰する人がいる。
例えばフィンセント・ファン・ゴッホ。
画壇から全く無視され、弟テオの庇護のもと絵画に没頭するが、生前売れた絵は1枚とも2枚ともいう。
それも友人の姉が買ったとか、弟が2枚買ったという伝説的な画家だが、
20世紀以降、ゴッホの絵は大きな評価と価格で世界の美術界に屹立している。
誰がゴッホの芸術を見出し、世に送り出したか私は詳らかではないが、その人物がいなければ私達はゴッホという芸術家を持つことはなかっただろう。
陶芸における「澤田痴陶人」という人物もゴッホによく似ている。
周辺の人を除いてほとんど名を知られることなく没し、20年の歳月を経て突然よみがえった人物だ。
1997年5月から3か月にわたり、日本人として初めて大英博物館で個展を開いて俄然脚光を浴びた人物だが、
没後20年を経過してその名と作品が広く知られるようになった。
ここで「人物」という語彙を用いたのは、本人が自らを「意匠デザイナー」とか「職人」と位置付け、
「作家」という名称を冠しなかったことによる。
知られているように、痴陶人を発見し世に送り出したのは大英博物館の東洋美術部長ローレンス・スミスだが、
日本の殆どの陶芸関係者や愛陶家が、生前はもちろん死後も<彼>を発見、評価をすることなく、
「逆輸入」のような形で痴陶人芸術を知らされたことは、
よく言えば、それだけ日本陶芸の裾野の広さや奥の深さを物語ると言えるだろうが、
「負うた子に浅瀬を教えられ」たような微妙な思いや情けなさを禁じ得ない。
やきものの批評家や愛陶家が日々渉猟を重ねても、痴陶人を発見できなかったということは、
やきものに関する日本の審美眼が劣化しているとも言える。
特に批評家と言われる立場で、生前の痴陶人を評価していたのは数人に過ぎない。
肩書や経歴に幻惑され、目の前にある事実(美)をありのままに捉えることが出来ないのは、
何時でも何処にでもあることだが・・。
ローレンス・スミスは、痴陶人が死後も長く「発見・評価」されなかった理由を以下のように記述している。
「ひろく一般的な注目を向けさせる力となるような背景が(中略)痴陶人に欠如していた」として、
具体的には
1 有名な美術学校を出ていない
2 後ろ盾となる有名な師匠がいない
3 名を継承する師弟関係をつくらなかった(息子は早世)
4 ほとんど展示をしなかったから有名画廊の支援がなかった
5 団体や協会に所属しなかった
6 地元でさえ有名でなかった
7 いかなるリストにも名を連ねず批評家などの注目を集めなかった
8 本人が宣伝したり、認められることに熱心でなかった
などなどのマイナス要因を羅列している。
これらのまったく陳腐な理由によって、私たちは痴陶人という人物(作品)を正当に評価することなく歴史の彼方に押しやってしまったのだが、
一人の外国人の努力によって痴陶人を歴史の中に甦らせてもらった。
ローレンス・スミスはまた、その『「評判」を作る』のなかで次のように述べている。
「結局のところ、生きているうちに認められるか、ずっと後になって認められるかは、歴史的にはたいした問題ではない。
真の才能は最後にはかならず真価を認められ、評価される」
このローレンス・スミスの認識を私たちは信念として持ち続けたいと思う。
絵画においても痴陶人と同じく、死後「発見・評価」された日本画家に田中一村がいる。
痴陶人と同じくNHKの「新日曜美術館」が取り上げ全国的に認知されたが、
埋もれた作家や芸術家を自分の目と足で発掘し世に送り出した人々(田中一村の場合は南日本新聞という地方紙のようだ)の情熱には、
ただ脱帽するばかりだ。
埋もれていた二つの才能が世を去ったのは奇しくも同じ1977年。
世に認められることなく、ひたすら自分の好きな道を歩み無名のまま世を去ることに、
おそらく二人は少しの悔恨もなかったと思う。
ふたりはただ美のミューズに導かれるままに美を創作した。
私たちは殆ど誰もが歴史的には無名のまま死んでいく。
この事実を了とせず名を残そうと努力する人もいるだろうし、無名のまま死ぬことに何の心残りを持たない人もいる。
煙のように消えていくか、幾ばくかの痕跡を残すか、どちらにしても<生>にとっては「たいした問題ではない」。
特に美を生み出す人間が、美を深化させようとする情熱は彼らの<業>のようなもので、
社会に「認められる」ことは相対的なことに過ぎない。
さて、
4月になったら澤田痴陶人の「万暦意五彩 花瓶」を掲載する。
生地は早世した子息の「澤田 じゅん」のろくろによるもので、この器体も他の痴陶人の袋物作品に共通するおおらかでゆったりとしたシルエットで、
いかにも「澤田 じゅん』らしさがよく出ている。
余談だが、私のような几帳面で小心な性格の者には決して挽けそうにないシルエットだ。
ご期待頂きたい。
↓
20年ほど前の焼き締め四耳壺
陶芸を始めて1~2年ころの紐作りの壺。たまたまスタッフが間違えて撮影してくれたので掲載した。
大きな作品を一心不乱に紐作りできたのは、情熱もさることながらなにより体力があったのだろう。
大き過ぎる壺(H=38.7cm)は場所は取るし、扱いも大変だから引き取り手がなく今もって実家の片隅に立っている。