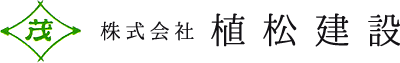見えないもの
自分の眼で自分の<姿>を見ることは出来ない。
<姿>という語彙を用いたが、他者の表情や動きを見るように自分の表情や動き,身体全体を見ることは出来ないということだ。
もし他者と相対している自分の姿を自分の眼で見ることが出来たら、
そのことだけでひとはもっと深く自分を知ることができるだろう。
手や脚といった身体の部位は見ることが出来るのに、なぜ一番見たい「その時々」の自分の顔や全体像を見ることが出来ないのか、
子供の頃からいつも不思議であり不満でもあった。
少年期、自分というものを掴み始めていく過程で、自分の眼に映る外部世界がまったく変化しないことが不思議だった。
長じて、老いの過程に入っても眼に映る外部の風景や他者の姿には全く変化がない。
もちろん加齢に伴う「老眼」などの話ではない。
網膜(脳)に映し出される外部の世界が、幼少期から現在まで私の年齢や成熟に応じた「変化」を少しも示さないということだ。
身体や心が老いるように、目に映る外部の世界が、例えば色褪せてきたり委縮したりという老いの徴候を映せば、
私たちはもっと豊かに老いることも出来るはずだが・・。
何かの折、自分が写った写真を見ると、自分が認識している自分の顔や表情と比べギャップを感じることがある。
鏡などで見て自分の顔や表情と認めているものと、写真に映し出された自分との違い(小さな違和)はきっと誰でも経験したことがあるだろう。
私が認識している「私の顔」と他者が認めている「私の顔」との間にも、きっと同じようなギャップがあるのだろうと思う。
残念なことに、ひとは誰もが他人が認識している「私の顔」や表情を知ることは出来ないが・・。
私の<姿>は、私にはイメージ(像)としてしか認識できないから、
他者の眼に映る(他者が認める)私の<姿>との間には宿命のように乖離があるだろう。
ことによると私が認識している私は、私だけのイメージなのかもしれない。
他者の中に存在している私を、私が可視化できないということは、
「私が認識する私は、私だけのイメージでしかない」と思いを膨らませることもできる。
これは<姿>だけでなく、なぜ私が思う私と、他者が認める私との間には乖離または差異が常に存在するのだろう。
この乖離や差異の中に社会的存在として生きる人間の<悲劇>があり、おそらくこのカオスの中に自己表現に係る源泉(表現への欲求)があると思われるが、
自分が認識する自分と、他者が認める自分とが「私の総体」とすれば、私たちは二つの自分を生きているような思いすら抱くし、
その両方が自分だと言えば簡単ではあるが、いつまでも違和感は消えない。
自分が認識している私が、同じように他者には認識されない永遠の要因とはなんであろう。
安倍公房の『他人の顔』を二十歳前に読んだ記憶がる。
今思えば十代のガキに理解可能な小説ではないが、背伸びして読んだのだろう。
事故で顔に大きな怪我をした男が精巧な仮面を着けて「他人」になり、自分の妻を誘惑するが、
妻は仮面の男が夫であることを知っていたという物語だった。
浅い読み込みの中での当時の感想は、「顔の喪失は存在の象徴の喪失」ということだった。
身体の部位の中で、一番その人間を象徴的に表すのは顔だという意味の感想だった。
多感な年代だから「顔」という<具体性>に過剰な思い入れをして読んだのだろう。
いまなら違う読み方をするだろうが、いま眼の前の世界を見ている「私の顔」を私が見ることが出来ないという事実は、
「見る」ことによって多くの情報を獲得する私たちにとって、自分の「顔」(私の存在の代表的表象)が、
実は「他人に所属する記号の一部」ではないかという妄想すら引き起こすし、
永遠に自分を客観視できない存在として私たちは存在している思いさえする。
自分を客観視できる人間など居ないのではないかという思いはずっとあったが、
客観視できる「方法」さえ手に入れることが出来れば、
自分の姿を自分の眼で見ることが出来れば、
または「三番目の眼」を誰もが持つことが出来れば、
この世の中の殆どの<悲劇>も消滅するのではないかと思うのだが・・・。
いま世界を覆う信仰が生み出す<悲劇>を消滅させる「方法」を、私たちはどのように見出せるのだろう。
「おまえはおまえの切符をしっかりもっておいで。
そして一心に勉強しなくちゃならない。
・・・中略・・・
みんながめいめいじぶんの神さまがほんとうの神さまだというだろう。
けれどもお互いほかの神さまを信ずる人たちのしたことでも涙がこぼれるだろう。
それからぼくたちの心がいいとかわるいとか議論するだろう。
そして勝負がつかないだろう。
けれどももし、おまえがほんとうに勉強して、実験でほんとうの考えと、うその考えを分けてしまえば、
その実験の方法さえきまれば、もう信仰も科学と同じようになる。」
宮澤賢治『銀河鉄道の夜』
↓10月の薪窯で辛うじて採れた(生き残った)作品。
個人的には自然灰のあまり掛かっていない、土味の残る作品の方が好きだから悪いものとも思わないが、
火燃しの仕上げ段階で棚組みが崩落し、途中で焼成を終えた分だけ面白みに欠けるかもしれない。