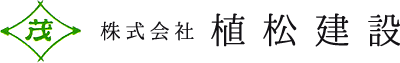神の手を持つ人
物作りに携わる人に付ける形容(称揚)として、最高の表現は「神の手を持つ」という言葉に尽きると思う。
陶芸の世界でこの冠詞が付いたのは、私の知る限り岡部嶺男と村田陶苑の二人だけだと思う。
私自身はこの二人以外に村田亀水先生を含めるが、3人ともその生涯に作った多種多彩なやきものは枚挙にいとまがない。
3人の代表作と言えば、岡部嶺男は米色青瓷、村田陶苑は陶彫、亀水先生は煎茶器若しくは月白青瓷になろうが、
これらに至る間に3人ともありとあらゆる種類の作品を生み出している。
3人に共通する点は、顧客のどのような注文にも応えることが当たり前の前提だという信念だと思う。
村田陶苑先生は2002年(平成14年)に97歳で亡くなった。
生前の言葉通り、職人の人生を全うした生き方だったと思う。
亡くなる2週間前まで作品を作り続けていたというが、生前一度だけ工房でお目に掛かったことがある。
亀水先生が親戚になるので、亀水先生にお願いして同伴してもらいA氏と私がお尋ねした。
90歳は過ぎていただろう。
非常に穏やかな話しっぷりで、小柄な先生が作る力強い陶彫作品とのギャップに不思議な思いがした。
工房も窯も小さなもので、ここから通を唸らせる作品が生まれるのかと感動した思い出がある。
当時先生の陶彫作品は、銀座和光で販売していたがひとつ600万円していて、
情けない話だが、その時は「金額の窓」から先生の作品を見ていた気がする。
実際、値段に換算して物の価値を把握するというのは、この社会では一番判り易いから便利なのだが、
利休が農民の生活品である「種壺」に美を見出したように、値段に換算されない美を見る素養を付けないと、
どうも人間が卑しくなっていけない。
工房でお茶を頂く段になったら、A氏が陶苑先生の使っていた染付茶碗を欲しがり、他の類似品は嫌だと駄々をこねだした。
金持ちが老人の宝を金に飽かして奪うようで、その場にいて居心地がよくなかったのも思い出だ。
他の作品との違いがまだ私にはよく判らなかったが、A氏にすると作り手が手元に置くほどだからという思いがあったのだろう。
向かうところ敵なしのA氏らしいお願いで本人以外は唖然としたが、いかにもA氏らしいと私は感心した。
A氏がその後その茶碗を手に入れたかどうかは分からない。
陶芸作家と言われる人たちが、出色のアガリの作品を自分の手元や家族で保存するという姿は、
少なくとも私の知る作家では見たことがない。
以前若尾先生が趣味で色絵の梅瓶を数本作ったことがある。
たまたま拝見して安価で分けて頂いた時、夫人が自分も欲しいのだが貰えないと語っていた。
何となく物作りに携わる人の姿勢を見たような気がする。
おそらく作り手にとっての作品は、それを購ってくれる人が優先ということだろう。
ちなみに、若尾夫人の宝物は先生が若い時分に作った「赤志野鉢」だった。
あれだけ多くの作品を生み出した亀水先生も手元にある作品は少なく、夫人の宝物は小さな青瓷の花生だった。
もっと大作もアガリの良いものもあったはずだと考えると、生み出した作品に対する作者の厳しさのようなものを見た気がする。
「家族は二の次」というと語弊があるが、良く出来た作品ほど他人に持って貰いたい、大事に使ってほしいという思いはよく判る。
アマチュアの私も自分や家族が使うものは完品でなく、何処かに疵があったりするが割るには忍びないというものばかりだ。
身内のために作ることが億劫な訳でもないのだが・・。
↓考えてもいなかった赤が発色したのだが、温度を上げ過ぎて釉薬が流れ、
割ってしまうには何となく惜しいので高台部分の釉薬を削って漆で補修した。
湯呑みなどは釉薬が流れずに採れたのだが、どういうわけかこの壺だけ流れてしまった。
いい色だと思うが、この手のものは人様には渡せないので自分が使うしかない。
作り手の手元にあるものはこうしたものが多いと思う。