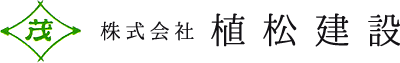<違和>の先へ
ひとは生きていく過程で、どこかで時代や社会の規範や価値、常識といった<共同的観念>と相容れない場面に出会う。
早い話が、いつも時代や社会と合致した価値やモラルで一生を過ごせることはないということだ。
社会的価値や常識に従って、「生まれ、生き、老いて、死んでいく」ひとのイメージを、思想家は『大衆原像』と概念化したが、
また、誰もがこの『原像』から多かれ少なかれ、逸脱してしか生きられないと彼は看破している。
個人の考えや価値がどこかで社会や時代の価値やルールとぶつかってしまう時、ひとはどのように行動するのか。
不本意であっても自分の考えを抑え、社会の側に合わせる人もいるだろうし、
自らの信念に従い社会からの孤立や反撃に耐えて、不如意な時間を過ごす人もいる。
「自由な意志は選択する」(マチウ書試論)からだ。
もちろん個人の「意志による選択」は相対的なものであり、個人が負う諸関係こそが絶対的根源だ。
誰もが多かれ少なかれ持つ社会との<違和>は、その<違和>に言葉を与えようと突き詰めれば、思想や文学の母胎となる。
社会との折り合いが上手くいかない時、ひとは初めて「社会という対象のなかに自分という存在を掴む」萌芽を見出すと言ってもいい。
社会と折り合わない自分と、自分に合わない社会や他者との葛藤を見つめようとする時、ひとは初めて「社会的存在としての自己」の契機に出会う。
文学や思想と言われるものが、どこかで「反社会性」「反権力性」を必然として内包してしまうのは、
文学や思想の営為が自己の内面に向き合い、社会や他者との<違和>を掘り下げ、
自分の<違和>に根拠(価値)を与えようとする行為に他ならないからだ。
時代の開放度や社会の成熟度によってその度合いは異なるが、権力が文学や思想の表現に外枠を設けようとするのは、
「社会的秩序の安定(イコール・権力の安定)」を維持するためだからであろう。
「社会主義国」と言われる地域で、文学や思想からソーシャルメディアと言われる範囲まで、
すべての表現にチェックが及ぶのは、時代の解放度や社会の成熟度の低さを示す指標といえる。
これらの地域の指導者たちが「社会秩序の安定」と言いながら、実は自分たちの権力の安定を目指していることは誰もが知っていることだ。
文学や思想がその本質として持つ「反社会性」や「反権力性」は、
表現者の内なる混沌(想念)が、社会の価値や常識という<スケール>では測り切れないという根拠による。
文学や思想が個的営為としてしか成立しないのは、<違和>を出自とする想念を推し測る<スケール>を、
<違和>を持つ自分が自分自身で創造しなければならないからだ。
近代以降、「作家」という立場は最もヤクザな「身過ぎ」だった。
作家の頭の中に渦巻く想念を言語化するという営為は、額に汗してものを作り商う大衆からすれば、
訳のわからない仕事であっただろう。
しかし、大衆が「作家」という立場を本能的にヤクザな「世過ぎ」と見なしていたのは、
「作家」という立場が、大衆が日常を依拠する社会良識(価値)や権力、秩序に向かって毒を吐く人種だと知っていたからだろう。
私たちは普段、社会という秩序や価値に寄り添って生きることが、「健全」で「安全」だと考えている。
だから、そうしたものと相いれない場面に遭遇しない限り、あまり社会や他者の在り様(イコール・自己の内面)を考えることもない。
一生をそのように生きられれば、きっとそれがいいのだろう。
職業的生活の時間を過ごせば一日は終わるが、文学や思想は一日のある瞬間に社会や他者の在り様(イコール・自己)を問う契機として、
突然出現する。
この契機を掴むか見逃すかは、「意志による選択」に負うことが多い。
今回は、「狂犬」百田尚樹の最近の発言について、批判をまとめるつもりだった。
きっかけは、「政治と宗教」の話はタブーとされる商談の中でたまたまこの男の話になった時、「こいつパーですね」といった客がいた。
あえてこうした踏み込んだ発言をする人には信頼を置くひねくれた性格なので、その日少し気分がよかった。
だが、お調子者のこの男をその行動や発言で「パー」というだけでは、このパーの発言が持つ時代の<姿>は捉えられない。
このパーを現在の日本の<姿>から捉えて批判しない限り、「莫迦につける薬はない」くらいではこのパーは止揚できない。
私の方にもう少し時間が必要だ。
(自然釉水指)