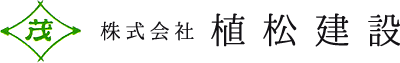いのち・ぼうにふろう その1
『いのち・ぼうにふろう』は仲代達也主演の時代劇映画。
何時、何処の映画館で見たのか記憶は全くない。
学生時代つまり40年以上前に観た映画。
覚えているのは、原作が山本周五郎の短編ということと衝撃的な題名、
モノクロ画面で白黒のコントラストを強調した画面処理をしてあった、ということくらいだ。
作者が白と黒の対比を強調したかどうかは不明だが、
記憶では、暗い画面に登場人物たちの衣装が妙に白々しかったこと,
そして、役者の動きが歌舞伎のように仰々しく、大時代的な感じがしたことくらいだ。
その記憶すら実はあやふやなところがある。
観たのはおそらく20代前半だろうから、今より感受性は豊かで、
「いのち・ぼうにふろう」というその言葉に強く魅かれたことだけが鮮明な記憶だ。
自分のいのちを投げ出し、自分にとって世界が<無>になろうが、
「いのちに代わる価値がある」というテーマは、20代の私にとってとても新鮮で魅力的だったが、
「いのちを超える価値」というテーマは、
いつだって日本人の民族的情念や美学が生み出す「ものがたり」の伝統的モチーフかもしれない。
こうした情念や美学は、日本の社会が高度消費社会に入るに従いしだいに社会から追放され、
今では時代小説と少数のハードボイルド小説などに存えているだけだ。
もちろんこの種の情念や美学が生んだ作品は、それらがもてはやされた時代(1960代から1970年代だろう)に在ってさえフィクションだが、
フィクションがフィクションとして、まだ人々の心の中に棲むことが出来る土壌があったのだろう。
こうした日本的情念や美学が生み出した作品が社会から徐々に消えていったのは、
日本が高度な消費資本主義に入っていった時期、
(象徴的なものがペットボトルの「水」が販売された頃)と軌を一にしていると思う。
最近、政治的意図を持ったような日本的情念や美学の「表現」が見られるようになった。
感覚的に言えば、上から目線の啓蒙的な(知ったかぶった)「表現」だ。
この手のトリッキーで、特定の部分だけをやけに強調する評論や映像、文芸作品は、
作品それ自体の質は低いが、結構もてはやされている。
分かりやすいからだろうか。
この手の情念や美学を内包した作品は、冷静に自分の中で消化しないと心を高揚させられたり、
カタルシスされる分だけ、あらぬ方向に私たちのこころを誘導される危険性がある。
いい例が「特攻隊」の美化だ。
理由は不明だが、(彼らは「特攻隊」は今日の日本の繁栄の礎などと言う)奇妙に「特攻隊」を美化する輩がいる。
戦術としてひとつの命を投棄し、それ以上の戦果を生み出す(出そう)とする「戦法」はおそらく、
民族や国家や集団の闘い(戦争)が発生したずっと昔からあったと思う。
『一殺多生』はいつの時代も、追い詰められた人々にとって、起死回生の逆転を夢想させる戦術かもしれない。
この「戦法」を実行する様は、殆ど毎日テレビで放映されている。
中東の「自爆テロ」がそれで、この手のニュースが報じられ始めた頃、
時代錯誤の愚劣な「戦法」で厭な気持になった。
最初は日本の「特攻隊」を真似たものかと考えたが、おそらく『一殺多生』の戦法は「特攻隊」以前からあっただろう。
「自爆テロ」と「特攻隊」がよく似ている点(点は点でも、濁点であり汚点である!)は、
「自爆テロ」や「特攻」を命ずる(命じた)立場の人間が、実際は彼らが会ったこともなく、
その意思を確認したことのない「神」や「天皇」を騙り、若い青年や少女に自死を強いることだ。
この手の「戦法」はそれを命ずる側はいつも死ぬことがない。
片道の燃料と爆弾を抱え、自らのいのちを捨てて父母兄弟や、友人、故郷を守りたいと死んでいった若者たちのこころは
誰にとっても尊いが、彼らを先立たせ、「後から必ず行く」といって生き延びた上官たちが多くいることは忘れてはならない。
何時だって、純粋なこころを利用する輩はいるが、利用だけして逃げ延びた上官たちが多くいた、
という事実に頬かむりし、死んだ青年たちを美化するとしたら、彼らは決して浮かばれないだろう。
今更ながら、物事が持つ光と影の両面を検証したうえで自分の判断を出さないと、
意図的に光の部分だけを美化する輩の思うつぼになる。
保坂正康によれば、「陸大」出のエリート軍人達は、自分の息子を「陸大に入れれば戦死は免れる」と言っていたという。
また、ある期の「陸大」出身のエリトー参謀50名のうち戦死者は4名だそうだ。
まったく、こんな連中が指揮をしたから多くの死を無駄にして戦争に負けたのだ!
彼らが敗戦を上手く逃げ延び、戦後巧妙に復活したという事実も含めて、
「特攻隊」の評価をしないと、死んだ(死なされた)青年たちの思いを無駄にすることになる。
続く
(自然釉耳付き花生)