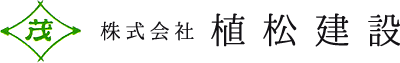老いの果ての死
6/18に母が91歳で亡くなった。
去年の3月末、入居していた老人ホームから体調を崩して病院に移り、
その時点では随分衰弱していたから1~2月の余命と覚悟していたが、点滴とカテーテルだけで1年2ヶ月以上永らえた。
91歳という年齢は、一般的には天寿を全うしたという見方になるだろうが、身内としては1日でも長くというのが当たり前の心情だ。
ただ、14か月という時間は「終末医療」という点から見て、老いた母には長すぎたと思うし、
「老いの果ての死」としては過酷過ぎる時間だったと思う。
入院の際に医師から「延命措置」を問われ、「不要」と答えた。
自力で寿命を全うしてほしいという意味だけで「延命措置不要」としたのだが、
母の姿や治療の様子を見るにつけ、どこまでが「延命措置」なのか、患者の家族はもちろん実は医師すら明確でないと感じた。
私としては、人工呼吸器のような医療機器に依存し、意識もなく肉体だけが機械の力で「生かされる」ことは不要だと考えた。
「助からない命ならば、痛みや苦しみは短い方がいい」という、誰もが思う気持ちを「延命措置不要」という答えに込めたつもりだ。
細っていく生命にどのような医療を施すのかという問題は、畢竟家族など判断者の死生観に左右され、当人の意思はあまり反映されない。
『延命措置不要」という判断は、母の意思ではなく私の判断だ。
衰弱した身体に点滴やカテーテルで薬や栄養を送り体力を回復することは、「延命措置」になるのだろうかと考えたが、
答は出なかったし、結果として母を14か月ベッドで過ごさせてしまった。
先の見通せる命に、点滴やカテーテルの施術をしてその都度痛みを与えたことが、いまも悔恨と疑問として残っている。
「自然死」は死の形として誰もが願う姿であろうが、突然ポックリ死ぬということでもない限り、
病院のベッドで何らかの治療を施されながら、死を迎えるというのが現代では一般的だろう。
「自然死」とよく耳にするが、どこまでが自然かさえ不明だ。
病室から毎日変わらない景色(窓からの風景は病院の壁と少しの空だけだった)を眺め、
ベッドから動くこともできない14か月はさぞつらかっただろうと思う。
いつも夕方様子を見に行ったが、私の記憶にある母らしい動作や言葉は入院半年を過ぎたころからもう殆ど無く、最後は一日の大部分を眠っていた。
母の姿に、ひとは生き永らえることが必ずしも幸福ではなかろうと感じたが、もちろん私の勝手な感じ方で母の気持ちは分からない。
父も100日余りの入院の末亡くなったから、両親は身をもって現代社会の、「老いの果ての死」の「典型」を私に示してくれたと考えている。
見舞いの帰りいつも思ったことは、突発的な死に遭遇しない限り、私も死に向かって希望のない数か月を病院で過ごして死ぬだろうということだ。
「末は60日」という、私が理想とする死生観を表す言葉があるが、はたして望みどおり逝けるかどうか。
ベッドで寝たままであっても、医学の力(栄養の補給)と体力(母はおそらく内臓が丈夫だったのだろう)によって1年以上生きた現実は、
当人にとって幸福なのか、それとも苦痛なのか、そう遠くない自分の姿として考えざるをえないが、
老いて病院で治療を受けながら死ぬということは、「自分のものではなくなった死」を生きることになるのだろう。
自分の意思に関わりなく、「臨終」が医学的に成立するまで生かされる現実は、やはり自分の死であるにもかかわらず、
自分の手から離れた死ということになると思う。
母は自分で点滴やカテーテルを望んだのではなく、母の意思に関係なく(自分の思いを口にできる状態でもなかったが)、
医者と私が話し合って決めたものだが、この時点で母は「自分のものでなくなった死」を生きることになった。
身体じゅうにに繋がれたチューブを自分ではずし、「いまから俺は死ぬ」と言って死んだ文学者がいたが、
こういう死に方は特別な人間の矜持なのだろう。
わが身に置きかえれば、老いて入院しその先にある遠くない自分の死に対し、作家と同じ矜持を持ちたいとも思うが、
たぶん作家は例外で、私にそれだけの度胸があるとは到底思えない。
ガンで余命数十日という友人を見舞った際、友人が「どうせ助からないからここから飛び降りようと思ったが出来なかった」と言っていた。
飛び降りようと思っても出来ないという思いは、スーと私の心に入りよく理解できた。
誰だって死に限りなく近づいてもそんな度胸は持ち合わせないだろう。
この齢になれば、多くの身近な死に立ち会うが、私がどのような死を迎えるにせよ、
「なるようになる」と受け入れればいいと思い、自分の死の姿にはあまり拘泥しない。
7/21、6月初めに工房に飛来した2組目のツバメがいなくなった。
前のツバメが巣立つ時は、ヒナが工房の中で何度も飛行練習をし、夜も巣に戻って数日たって巣立って行ったが、
今回のツバメ3羽は、飛行練習もまったくせず7/21突然姿を消した。
昨日巣の中にうずくまっていた3羽が、翌日から全く姿が見えなくなったのだ。
その後電線に止まったツバメを何度か見たが、巣立ったツバメかどうかは不明だ。
この夏の猛暑にうんざりし、かつ時々下からの電気窯の放熱に晒されたから居られなくなったのかもしれない。
一度巣から落ちたヒナを巣に戻してやったが、そいつも旅立って行った。
「そぶりも見せず」という言葉があるが、ある時煙のように静かに消えるという行動パターンが昔から好きだったから、
こういう思い切りのいい別れ方が私にはすっきりしていい。
「つくべき縁あれば伴い、離るべき縁あれば離るる」という生き方に憧れるが、凡夫の悲しさゆえ過去の人間関係を振り返ることも多い。
前だけを見て生きていければ人間関係に悩む必要もないと思うのだが、うまくそれが出来ない。
巣立ったツバメがこれからどこへ向かうのか知らない。
来年こちらが望まない再会もあるかもしれないが、再会してもそのツバメが工房から旅立ったツバメかどうか確認のしようもない。
たまたま初夏に起きた出来事を並べた。
母との別れとツバメとの別れに何の関係もないが、時間だけは確実に早く過ぎていくことを強く感じた出来事だった。
↓食器、窯から出てすぐしまわれてしまう食器。
知人が持って行って配ってくれたがまだこんなに残っている。
花入や壺よりさばけるからいいが・・。