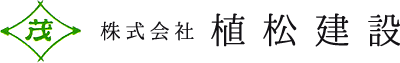ツバメ、そしてみたびの「束縛」
今年も工房の蛍光灯の笠でツバメが産卵し、5匹のヒナがかえった。
親指ほどのヒナが、親鳥が餌を運ぶたび大口を開けて餌を求める姿は、飽きることない見ものだが、
5個の黄色い口がピーピー大声を上げて一斉に開くさまは、まったく滑稽なものだ。
今年のツバメは、咥えてきた餌を一匹のヒナに全部やるのでなく、
何匹かに分けて与えているようで、例年のツバメとはエサやりが違うような気がする。
今年のツバメは頭が良いのか、効率的なエサやりをしているようだ。
4月の初めころ、最初のツガイが来て去年の巣を補強しはじめ、去年よりもしっかりした巣にリフォームした。
去年の巣は小さく雑な作りで、何度かヒナが巣から落ち、そのたび私がこわごわ脚立にのぼって巣に戻したのだが、
今年最初の巣はずいぶんしっかりした作りだった。
この調子では早い産卵が始まるかと思っていたが、暫くすると別のツガイ(?)が飛来してこの巣を壊し、
最初のツガイを追い出したようだ。
ツバメは人間ほど個体の識別がはっきりしないから、最初のツバメが追い出されたのか、
それとも後のツバメが巣を占拠できず、八つ当たりで巣だけ壊し諦めたのか不明だが、
たぶん後のツバメが種の保存競争に勝ち、営巣を始めたのだろう。
新しい占領者が前の統治者の建築物を破壊し、その後に自分たちの建築物を構築する様子は、
さながら中国や日本の戦国時代を彷彿させるが、こうした行動は生きるもの全ての本能的行動なのだろうか?
安住の地を追われたツバメはまた別な場所を求め、そこで再び同じ営みを繰り返しているだろうが、
動物の本能が持つエネルギーの強さに改めて驚嘆する。
ツバメに人間のような感情があるならば、全てを奪われ破壊されても別な地で再起を図るというエネルギーをもちえるだろうか?
執着心が薄く、復元力の小さい私などはおそらく不可能で、ただ疲労や喪失感に打ちのめされ立ち止まってしまうだろう。
工房の床には毎日ツバメのフンや土、羽が落ちていて、決して見栄えのいいものではない。
床掃除の頻度も増えて困ったものだが、小説「玄鳥」の登場人物のように、
巣を壊してヒナを追い出す(殺す)度胸が無い私には、黙って受け入れるしか途が無い。
もう暫くしたら活動が活発になるヒナ共の多量のフンの受皿と、巣から落ちてしまうヒナの為のセフティーネットの設置、
ネットの中のチェックとヒナが落ちた際の巣への戻しなど、巣立ちまで煩わしい思いをしなければならない。
この齢になって知ったことだが、ヒナ共はフンをする時に尻を巣の外に向け排泄する。
巣の中を大量のフンで汚さないようにということだろうが、身勝手なものだ。
自然を観察することなどなく追われるように生きて来たから、この齢になってツバメの生態を知るというのも赤面ものかもしれない。
今年で3度目のツバメとの付き合いになるが、それでも私から望んだ関わりでない分だけ煩わしさがある。
人間を筆頭に、生き物との関わりほど束縛が多いものはない。
妻が残した猫2匹の食事やトイレの世話の為、いつも家から離れられない身には、生き物に縛られる煩わしさがよく分かる。
向こう側からやって来る「束縛される関わり」は少ない方がいいが、人の世は思い通りにいかない。
「関わりたくないけれど、関わらざるを得ない関わり」が生きることの本質かも知れないが、
向こう側から来る「束縛」が何時までも続くのは、それを仕方ないと考える私のこころが引き寄せるのかもしれない。
笹沢佐保ではないが「あっしには関わり合いのないことで」と体をかわせれば、もっと人生は身軽になるのだが・・。
天才・ランボーは、「束縛されて手も足も出ないうつろな青春」(『いちばん高い塔の歌』)と多感な時期の「束縛」を表現したが、
青春が終焉しても、人は「束縛」という関わりから解放されるわけでもないようだ。
すがる家族を蹴飛ばして出家したという西行ですら、「世の中を捨てて捨てえぬ」と嘆いたのだから、
凡夫の我々が世の「束縛」から隔たるのは絶望的だろう。
ランボーは詩という「束縛」から逃れ、砂漠の果てに武器商人となって消えたが、
「こまかい気づかゆえに 僕は自分の生涯をふいにした」という、この天才の悔恨だけは御免こうむりたいものだ。
頭上でピーピー騒ぐツバメが、一日も早く巣立って、この関わりから解放されることを願うばかりだ。
↓白化粧の蹲壺
「焼き締め」をやる人は、殆ど誰もが一度はこの蹲壺を作る。
私はこの形が好きで何度も薪窯で焼成したが、なかなか気に入ったものが出来ない。
蹲壺は形が非常にシンプルで、かつ本歌は実用としての種壺、油壺で、
農民が農閑期に作ったものだからまったく作意が無く、それ故、後世の人が作るのが難しい。
この形の壺を「蹲る」と名付けたのも後世の茶人で、作り手の農民とは全く関係のない話だ。
今回初めて薪窯ではなく電気窯で作ってみた。
電気焼成の特性を考えて化粧掛けをしたが、
どうしても薪窯が醸し出す風情が出ない。