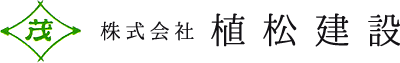エリートの陥穽
昨年秋から偶然が重なり、日本が太平洋戦争突入し敗戦に至るまでの歴史的な出来事について、幾つかの本と映像に出会った。
時系列的には、1936年の「2・26事件」についての数冊の本、
太平洋戦争で最も無謀な作戦と言われた1944年の「インパール作戦」のドキュメントとその解説、
戦争開始の昭和16/12/8の1日と、昭和20/8/1から終戦までの15日間を軍人、政治家、文学者、市井の人々の姿を膨大な記録から拾い上げた本、
8/15の玉音放送までの政治家と軍人の動きを映像化した原田眞人監督の『日本の一番長い日』など。
子供の頃の記憶を辿ってみると、日本の近代史について授業で細かいことを学んだ記憶はない。
例えば「2・26事件」について学んだことは、「ヒドクサクイヒ 2・26」という、
受験のために年号を覚える語呂合わせで程度で、「1936」年に陸軍の一部将校がクーデターを起こし、
東京に戒厳令が敷かれたということくらいだった。
何故、陸軍の一部将校がクーデターを決行し、背景に何があったのか、投降後(いわゆる原隊復帰後)どのようにクーデターが収束したのか等、
殆ど知らないまま大人になった。
「2・26事件」の理論的指導者と言われ、将校と共に銃殺刑になった北一輝については学生時代に興味を持ったが、
文章が難解すぎて私の知力では全く理解できずとん挫したままだ。
当時の小中学校のカリキュラムでは、社会科の授業時間はさほど多くはなかったし、
日本の歴史全般を知識として教えるには、大きな事件の年号を覚えさせるくらいで仕方がなかったのかもしれない。
学校教育は知識の外枠を作る作業で、中身は自分で埋めろということかもしれないし、
複雑な人間関係が<権力>を作り民衆を統治する歴史を、「人間関係の結果」として捉え理解するには、
歴史上の出来事に対する主観も含まれるから、おそらく評価の定まっていない近代史は教えにくかったのかもしれない。
「2・26事件」や「インパール作戦」、8/1から8/15までの間に起きた広島、長崎への2度の原爆投下とソ連の突然の参戦など、
日本人が体験した大きな悲劇の中で、歴史の舞台に登場し歯車を回したエリート軍人たちの思想と行動は、
結果的にエリートゆえの独りよがりの連鎖が、大きな悲劇を国民や兵士に強いたといえる。
彼らの行動や理念、善意が真面目で高潔であるほど、当事者や関係者にも悲劇の色合いが濃厚に浮かび上がってくるが、
これらの悲劇は、「皇軍」と呼ばれた日本帝国陸軍という組織にその源泉(欠陥)があるだろう。
敗戦は、国民の上位に位置した日本陸軍という組織が持つ欠陥が露出した「組織体としての敗北」であろうし、
「2・26事件」は尉官級の頭脳明晰で極めて真面目な青年たちが、ある時は上官に教唆され、ある時は客観情勢を見誤り、
自らと部下たちを悲劇に導いたと思う。
敗戦が軍事的敗北である以上に、日本の全思想の敗北であったという視点は、深く検証されなければならないと考えている。
欧米のアジア侵略は植民地に「文化」を生み出したが、日本のアジア侵略はかの地に何の「文化」も生み出さなかったという見方があるが、
この視点に立てば、敗戦が日本の思想的敗北であったと言っても良かろう。
「2・26事件」で処刑された将校たちの手記や残された妻たちの記録からは、
終戦とともにこの国から無くなった硬質の正義感や純粋さなどがよく窺えるが、優秀な彼らが要人を暗殺して目指したその先の国家像はよく見えない。
将校たちの目指したものは、明治国家を範とした「天皇親政国家」という言葉だけのイメージでまったく具体像はなく、浮遊しているだけに見える。
彼らの理論的主柱と言われた北一輝の『日本改造法案大綱』と、青年将校たちのクーデター後の国家像がどのようにリンクするか、
北一輝の「国家社会主義」という国家像と、将校たちの国家像、天皇像がどこで合致したのか、残念ながら私の頭では理解できない。
明治憲法における「天皇」の位置を否定した北一輝と、青年将校たちの目指した「天皇親政」がどこで思想的一致を見たのか、
今もって私には不明だ。
よく言われるようにクーデターの背景や目的には、陸軍内部の皇道派と統制派の主導権争い、
飢饉による東北地方の貧農の娘らの身売りに対する純粋な義憤、
彼らが「君の奸側」とあまり根拠なく考えた天皇周辺の政治家や権力者、財閥への不信、
天皇親政の実現による内政、外政における政治的閉塞感の打破などがあるが、
クーデター後の「親政」実現の道筋をまったく描くことなく、
その後の展開を上官たちの周旋(天皇への上奏など)に頼ってしまったように見える。
将校らにすれば「身を挺して」、「先駆け」になるという、焦りにも似た思いが強かったのだろうが、
暗殺計画の緻密な割には立てこもり後の計画性が見えない。
彼らの行動は、自分たちの忠誠と正義が必ずや天皇に届き、陸軍内部からの支持、連帯の呼応が起き、国民にも支持されると考えたのだろうが、
彼らが信じ、目指した正義すら陸軍内部において相対的なものに過ぎず、
クーデター後は皇道派の中心的な将軍たちをも沈黙させて一挙に孤立し、
反乱軍の汚名を着て投降していくさまは、純真さゆえの独りよがりが生み出した悲劇のように見える。
天皇は彼らの描いた思いとは逆に鎮圧を命じ、クーデターはとん挫した。
反乱将校たちは、銃殺刑になっても彼らの思想に殉じたと言えようが、
クーデターとも知らず、ただ上官の命令として行動した兵隊たち(多くは彼らが救済しようとした貧しい農民の子弟達)は、
武装解除後(原隊復帰後)に口封じのためか、南方の激戦地の最前線に送られそのほとんどが戦死している。
これも彼らエリート将校の痛恨の見立て違いといえよう。
この悲劇の要因の一つに強固な縦社会である日本陸軍の上下関係もあろうし、
士官学校出のエリート中のエリートであるが故の自己過信もあったろう。
彼らの現実の国民像の把握や視点、国家改造イメージは案外に皮相で、職業的世界としての複雑怪奇な陸軍と、
その頂点の神としての最高統帥者である「イメージとしての天皇」ほどしか現実的認識がなく、
救済の対象と考えていた国民すら、彼らの思想の中にその実体の姿はあまりなかったのではないかと思う。
選ばれた者たちは、その高邁な知性や理想の為、時に国民や部下を数やイメージとしてしか捉えず、
「衆愚」な我々大衆の現実と乖離を起こすことがしばしばある。
軍隊のような閉鎖的な共同性の中で繰り返されるエリートたちのこうした悲劇は、15年戦争の間続いたと言える。
日本軍のもっとも愚かしい作戦と言われる「インパール作戦」などは、
エリート軍人たちが、国民(兵)の命を単に数としてしか考えず、ただ自分の硬直した考えと愚かしいエリート意識で、
日本人同胞3万を死に追いやったとしか見えない。
インパール作戦を指揮した司令官が、作戦参謀に「何人殺せばインパールは陥落するか」と訊ね、
参謀が「5000人」と答えたという有名なエピソードがある。
この逸話はエリートゆえの度し難い傲慢で、「5000人」が日本兵の死者を指す数字だったのだが、
こんな人間しか指導者に持てなかったのだから、「民草」が悲劇を一身に背負うのは当たり前だし、
戦争に負けて当たり前だろうと思う。
何時の時代もエリートが陥る陥穽として、彼らが「数」としてまるで駒のように国民を見ていた結果、
国民だけが被る悲劇はいつまでも検証、記憶されなければならない。
太平洋戦争の数々の悲劇を生み出したエリート達は、「神国日本」という精神論をバックボーンに、
国民・兵士を「数」としてしか見なかった。
「選ばれた者たちの愚」は、
シモーヌ、ヴェーユの言う「戦争とは自国の指導者が、他国の兵士に自国民を殺させる行為」という根底的な戦争定義をひっくり返し、
「戦争とは自国の指導者が、指導者の愚かさで自国民を殺し、その責任に頬かむりすること」とでも定義出来ようか。
エリートが国民を指導するという政治構造も「歴史的暫定」としては「自然」だろうが、
彼らの明晰な頭脳が民衆の実態を把握できず、多数の民衆に悲劇を強いることは歴史が何度も教える真実だ。
明晰な頭脳と共に人間性豊かな指導者を持つため、我々がどうあらなければならないのか、そこがポイントになる。
「善意が善意であるほど悪意になる。善意が生活に媒介されないからだ」と喝破したのは誰だったろう。
↓最近の作品 鉄赤花入と一輪挿し
この形は手馴れている分だけ面白みに欠ける。
きっと見る方もそうだろう。
ここから先に進む独創性が生まれてこない。
才能が無いのは自明だが・・。