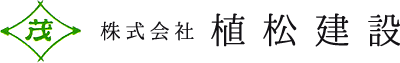基本に戻る
志野や織部、黄瀬戸といった日本独特のやきものである「美濃焼」は、日本の陶芸シーンでいつの時代も常に注目を集めてきたやきもので、
故に多くの名匠、名工を輩出し、いまも日本陶芸のトップランナーといっても過言ではない。
この分野にTという作家がいて、若い頃この作家の作品に接した時の驚きは今もって鮮明に覚えている。
この作家こそ歴史的に常に注目されてきた「美濃焼」を革新し、「美濃焼」の歴史に新しい1ページを加える作家だと思った。
私がやきものの美に魅了され、のめり込み始めた頃だった。
その後折に触れこの作家の作品を注視してきたが、小さな違和感を感じたのは作家がそれ以前の作風を意識的に転換し始めた時だ。
ピカソの例を出すまでもなく、作家は自分が生み出した芸術のスタイルを自分から切り離し、また新しい表現に転換していかない限り、
作家として全うし得ないから、Tが自らのスタイルを自ら壊し、新しい分野に挑戦することは作家の「脱皮」として潔いと思ったのだが、
新しい分野の作品は、かつて美しく力強い作品を生み出した作家が作るものとしては全く力不足で、到底考えられない噴飯ものだった。
当然作家には彼なりの目算やモチーフがあっただろうが、長年注目してきた私にすれば、
なぜこんなつまらない物しか作れなくなったのだろう、という不満とやりきれなさで一杯だった。
やきものに限らず、作家には2通りのパターンがあり、ひとつは自分の確立した表現方法を自ら捨てて新しい分野に転進するタイプと、
試行錯誤の末に辿り着いた作風に固執し、その分野の更なる深化を目指すタイプがある。
これはどちらがいい悪いという問題ではなく、作家の内なるモチーフや情熱が向かう方向の差に過ぎないが、
やきものの世界においては、前者の典型が岡部嶺男や清水卯一とすれば、後者は歴史的な窯業地(備前焼、萩焼など)で作陶を続ける作家に多い。
「美濃焼」という多くのカテゴリーを持つやきものにおいては、
例えば志野から織部に作風を転換することも、他の分野からの転出よりなじみ易いと思うが、
「美濃焼」の範疇で今までとは別な分野に移るという転換は、実はちょっと隣に移るという程短い距離ではないと思われる。
そしてこの転換に失敗すると、想像以上に作家が毀損されるような気がする。
あくまで個人的な見解だが、かつて私が天才と確信したTの現在の停滞した姿がそう感じさせる。
驚嘆すべき才能が、生涯にわたって開花し続けるという姿は、歴史的に見てもまれといえばまれだが、
若い頃に大輪を咲かせた才能が、その後色褪せる姿は枚挙に暇がないのが冷厳な現実といえば首肯せざるを得ない。
以前、何気なくTを思い描きながら若尾先生に、一流作家でも新しい作風にうまく転換出来ないことがあるかと聞いたことがある。
先生の答えは、基本がどれだけ確立しているかがポイントで、作家は誰でも迷走を繰り返しながら新しい作風を模索するが、
一歩踏み間違うと先の見えない迷路にはまって脱出できないことがあると言っていた。
特にある分野で自分を確立した(自分の美を確実に捉えた)作家ほど、転出は難しいということらしい。
迷路に踏み込んだ際、元に戻る方法は?との私の問いに、先生は「基本に戻る」と言った。
芸術という無から有を生み出す営為の繰り返しにおいては、当然ひらめきが下りて来ないスランプもある。
そうした際にも、唯一の脱出口は「基本に戻る」ということになるのだろう。
陶芸に限らず、文学や絵画、音楽等も含めすべての文化創造がそうだと思う。
趣味で好き勝手にやきものを作る私の立場では、高尚なスランプということもないが、
それでも好きな花入や壺が最近パターン化していると感じることがしばしばある。
新しいフォルムやカーブを作り出せず、以前の形が多く、少しだけシャープに成っていてもどうもマンネリになっている。
アマなりに上達したいから、いまは若尾先生の言葉に倣って「基本に戻る」ことを考えている。
私の場合「基本に戻る」ということは、湯呑みやカップを作りながらもう一度ろくろによる形の成形を考えるということになると思うので、
暫くはあまり好きでない湯呑みやカップ作りに打ち込み、ひらめきや再発見が生まれて来るのをじっと待とうと思う。
まあ、湯呑みやカップは人にあげてもかさばるものでもないから、花入よりは捌けるかもしれない。
↓鉄赤の小物
生地は鈴木三成先生のもの。
色見本のような感じになって面白みもないか。