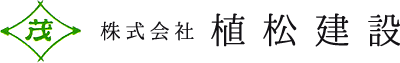正月の窯
例年のように暮れから正月にかけて山で薪窯をやるつもりでいたが、本業が忙しくて窯詰めが間に合わずに断念した。
薪窯の場合、成否は窯詰めで決まると言われるくらい窯詰めは重要な作業だが、
私の窯は中の背丈が低く、かつ一般的な階段状にもなっていない(若尾利貞先生の設計)ので、窯詰めが大変で時間もかかる。
薪窯のため秋口から作品を挽いて準備していたので、工房が素焼きの作品で一杯になってしまい、
仕方がないから薪窯用の作品を電気窯で何度も焼いた。
薪窯用の粘土は大概が荒土を用いるので釉薬用にはあまり適さず、焼くと釉薬の剥がれやピンホールが出来やすいが、
窯焚きをしない正月というシチュエーションも考えられないので、正月休みの間じゅう焼けるものはすべて電気窯で焼いた。
窯出しのあと釉薬の色が悪かったり、ピンホールがあったりするとすぐまた焼き直ししたので、何度窯のスイッチを入れたか記憶がないほどだ。
窯の温度が350℃位になると強引に蓋をあけ、次のものを入れたから正月中窯は稼働しっぱなしだった。
結果が以下の写真になる。
もともと、山で薪窯をやりながら電気の窯もやる予定でいたから釉薬用のものも作ってあったが、
簡単なはずの電気窯での焼成も成功あり失敗ありで、あらためてそれぞれの土に合った焼き方がいいやきものを作る条件だと再認識した。
「人には相応しき贈り物」というが、土には相応しき焼き方ということだろう。
九州の知り合いから「不知火」の原土を送ってもらったので、この土も薪で焼くつもりでいたが、結局電気で焼いた。
この土は黒味が強く、かつ原土ゆえ小さな石も交じっていて、ろくろ挽きの時は指の皮がむけるほどの荒土だったが、
焼いてみたら想像以上に耐火度が低く、1250℃位で溶け壺がヘタって鏡餅のようになってしまった。
その写真も以下。
土も見た目と中身は違い、焼成してみないとそれぞれの土の耐火度が分からないが、
各々の土には極点があり、それを超える負荷がかかるとヘタるということをあらためて学んだ。
何事も極点を上げる努力は常にすべきだろうが、極点を超えると全部がダメになることもあるということだ。
子供の頃から頑張れ、頑張れとケツを叩かれて育った世代で、時代もそういった雰囲気一辺倒だったから、
いまの若い世代のように、頑張り過ぎて「自分自身に追いつめられる」という経験は少ないが、
今思うと、努力不足で自分の極点まで近づけず、故にダメになることもなかったのだろう。
それにしても「貧乏人の子沢山」とはよく言ったもので、引き取り手のないやきものをまあ沢山作るものだと自分でも感心するが、
次回はもっといいものを作ろう、作れるはずだという作り手の<業>が多少なり私の身内にもあるから、
作品は溜まる一方になる。
老いるにつれ、もうこれ以上の進歩はなかろうと自覚した時が引き際かとも思うが、
例えば「画狂人・北斎」のように何時まで経っても自作に満足せず、あと5年、あと10年と「途上の思い」を持って、
殆ど引き取り手のないやきものを作り続けるような気もする。
窯出しの度にこれを見たら私が私淑している先生はどういう評価をするだろうか、ということをよく考える。
プロが見てどういう評価を下すか、ただそれだけのために作り続けるというのも、
楽しむために作るアマチュアの立場からすると奇妙な気もするが、
作り手の殆どは、自分の作品を理解する少数の人を思い描いて作り続けるのだと思う。
たったひとりの理解者を思い描いて作り続けることは、実は作り手の大きな根拠かもしれない。
↓ 暮れから始めた焼成は全部を焼き上げるのに1月下旬まで掛かった。
青瓷はそれなりのものが採れたと思うが、青瓷の宿命でどうしても薬が厚い分重い。
まあ花入などは持ち歩くものでもないが、他の釉薬ものに比べ重すぎる。
如何に軽い作品を作るかがこれからの課題になる。
2枚目は窯の中でヘタッタり、釉薬が飛んだもの。
壺がつぶれて鏡餅のようになっている。