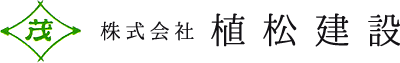国宝の青磁作品について(その3 飛青磁花生)
国宝のやきもの14個のうち3個が青磁作品ということは、日本人がいかに深く青磁作品を愛し続けてきたかという証といえる。
「飛青磁 花生」は元時代の龍泉窯で14世紀に作られて渡来し、鴻池家に所蔵されたのち稀代のコレクター・安宅英一の手に渡り、安宅産業倒産後、
債権者の住友銀行をはじめとする住友グループ21社から1980年1月、大阪市に他の国宝や重文と共にすべてが寄贈されたという有名な逸話を持つ作品である。
この作品は大阪市立東洋陶磁美術館で、天井から自然光を取り入れたコーナーに置かれ、
南宋官窯の八角弦紋壺などと並んで、一番その美しさを引き出すと言われる自然光の下で見ることが出来る。
陶磁学者の小山富士夫によると、青磁の作品は朝陽の中で見る時が一番美しいとのことだが、
この作品を朝陽の中で見ることが出来るのは美術館の関係者だけかもしれない。
この作品は所謂「玉壺春」と言われる典型的なフォルムをもち、豊かな胴(腰)からゆったりとしたカーブが立ち上がり、ほっそりとした頸部を経て、
日本人の感覚(美意識)から見ると少し小さいような気がする口作りに至っているが、
全体のバランスはどの民族の美意識を持っても首肯せざるを得ない絶妙のバランスで作られている。
高さは27.4cmでおそらく「玉壺春」と言われる形はおおむね30cm前後が一番美しいのではなかろうか。
写真で見る限り(残念ながら本物に触ることが出来ない)胎土は元時代特有の鉄分の多い赤褐色ではなく、薄い鉄色を呈している。
「玉春壺」に限らず、やきものは手に持った時の重さのバランスが重要なポイントになるが、特にこの形は重さのバランスが重要なのだが、
これも残念ながら触れることが出来ないのでバランスの良し悪しは不明だ。
まあこれだけの形を作れるのだからバランスも絶妙と思うが。
中国元時代のやきものは、騎馬民族と言われる民族性ゆえに「重厚長大」な作品が多く、日本人の繊細な感覚には若干の齟齬感をもたらすが、
この作品に限っては非常に繊細なフォルムを持っていてその釉色(いわゆる「天龍寺青磁」と呼ばれる緑の発色)と見事にマッチし、
見る者の心をとらえて離さない。
この形はやきものにとって永遠の基本フォルムであるから、その後も多くの「玉壺春」がつくられているが、
どの作品を見てもこの作品と比べるともう少し口の幅が広いような気がする。
現代の腕のいいろくろ師にこの形を見せ、ろくろを挽かせてみたら原寸よりも口幅が大きくなるのではないかと思っている。
現代と元時代の美意識やバランス感覚の違いであろう。
「飛青磁 花生」の一番の魅力は、その形と共に釉薬の上に散らされた鉄斑にある。
綺麗な釉薬の上に敢えて鉄色の斑紋を着けるという技法は、おそらく偶然生まれたものと思うが、
不思議なことに元以降はあまり用いられない技法のようで、
現代の青磁作家にも時折その手の作品を見かけることはあるが、余技の域を出たものは少ない。
悠果堂美術館にも、中国元時代の青白磁の茶入に鉄斑を施した作品を掲載しているのでご高覧頂きたい。
この花生の鉄斑は一見さりげなく置かれているが、実は緻密に計算された配置になっていて、
多過ぎず、少な過ぎずを見事に体現している。
青磁や青白磁に鉄斑を挿す場合や、土もの(備前焼や信楽、伊賀など)にヘラ目を入れる場合、
作り手はいつも抑制的にとブレーキを掛けながらやるのだが、終わってみると鉄斑やヘラ目が多すぎるきらいがある。
このことは備前焼の安倍安人氏も言っていたが、ひとつのヘラ目の不足感を補おうと2のヘラ、3のヘラを入れてしまうからだと思う。
「過不足なく」ということを実現させることは、作り手にとって永遠の課題かもしれない。
↓片身変り筒花入
何の変哲もない花入だが、この手のものが使いやすい。
作る方はあまり楽しくはないが。