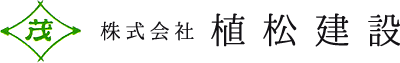個性と時代
「作家は処女作に向かって成長する」と言われるが、
処女作には作家の資質や思想、価値や美意識など、死ぬまで彼に付きまとう始源の要因が内包されているということだろう。
そして作家は内部に混沌として持つそれらの要素を、その都度の契機によって表現(言葉)すると考えている。
典型的な例が太宰治だろう。
太宰の処女作と言われる『晩年』には、ほとんど全てのエッセンスが内包されている。
やきものの世界でも同じことが言える。
作家の初期段階の作品には、彼らの後年の到達点を彷彿させるケースが多い。
なにより、ろくろのくせやカーブのライン、全体のバランスといった特徴は、
後年彼の「腕」が上がっても、殆ど変ることなく初期作品に見て取ることが可能だ。
「雀百まで踊り忘れず」ということだろうか。
個人の美意識は<美>に触れるほど豊穣になるが、根幹にある美は生涯変わらないのかもしれない。
やきものが文学と少し異なる点があるとすると、やきものの場合「破綻を目立たなくする」大きさや形状があるようだ。
だから、あるものを作らせると非常に美しいものを生み出すが、別の大きさや形のものを作ると見るに堪えない作品になる作家も多くいる。
花生ばかり作っているからか、私の場合は茶碗を作ると10にひとつも良いものが出来ない。
一流と言われる作家はまた、ある日突然大きく変化する。
地下に溜まったマグマが突然吹き上げるように、それまでかすかな変化を繰り返していた作品が、
突然全く別人の作品のように変わることがある。
だがそれとて、どこかに必ず前作(若作)がもつ要素(個性)を垣間見せる。
私の好きな清水卯一のように、自分のスタイルを自分で壊し(放棄し)次々と新しい分野に挑戦した作家であっても、
その「到達点」の中に、作家が通ってきた「通過点」がよく見て取れると思う。
自分のスタイルを壊さず生涯をそれで通す人、
次を求めて「現在」を壊して迷路に入り込み、二度と元に戻れない人、
やきものの世界にも様々な作り手のドラマがある。
むかし怪しげな骨董屋に「桃山の壺」を見せられたことがあった。
古美術の世界では「桃山」と名がつくだけでブランドになるが、当然その分だけ贋作だらけだ。
まだ陶芸を始める前のことだが、骨董に多少の知識があったので、「桃山にしては作品の力が弱いのではないか」といったところ、
「同じものを作っても体調の悪い時もあるはずだ」と反論され、それも一つの見識かと思ったが、
いまなら決してそうは考えない。
やきものは時代によって共通の特徴的なポイントがあり、そのポイントを外してはその時代にその作品が生まれないほど、
時代が醸し出す美意識や感覚が作り手の意識の底に染みついている。
だから、体調が悪くとも作り手の時代感覚や個性が生み出す特徴は変わらないと思う。
「陶は政なり」という中国のことわざは大げさな表現にも聞こえるが、
明や清の時代のやきものなど、権力者の美意識や時代の混迷をしっかり映しているから不思議だ。
備前焼や志野焼は作家の贋作が多い分野だが、どのように巧妙にコピーをしても
作り手の個性がどこかに出ているから、別の作り手には当然それだけは表現できないようで、
少し作家の作品に触れた経験さえあれば、誰でも贋作に違和感を持つことが出来る。
作り手が異なれば、うまく模倣をしても作り手の個性がどこかに出てしまうということだ。
共同窯で焼いていた時期、数人の作品を窯出しする際に誰もが正確に仕分けることが出来た。
銘の部分が灰で隠れていても名を見ることなく作り手を特定できたが、
同じようなものを作っても技術のレベルに関係なく、必ず作り手の特徴が出ていて個人が物を作る不思議さを何度か味わった。
一人一人の人格が異なるように、ひとが手で作るものは目の前にその物をおいて模倣をしてもなかなか同じものが出来ないと思う。
やきものは時代の雰囲気や感覚を映す(映してしまう)ものだが、
最近の若手の壺などを見ると、大きな特徴として高台が小さく、細身で背の高いものが多い。
一見するとシャープでスマートだが、どうも作品としての安定感に乏しいと思う。
現代が持つ「不安感」が、無意識のうちに作り手の感性に投影しているからではなかろうかと思っている。
社会が持つ息苦しさや不安感が、無意識のうちに作品に投影される時代は作品にとっても不幸だ。
ある時代のある環境の中に生まれたという偶然は個人ではどうしようもないものだ。
豊かな時代の豊かな環境に生まれた者が、ゆったりとおおらかな作品を作り出すのは、
結局文化がそれぞれの時代の雰囲気を、作者の意図に関わらず間接的に映し出すからだろう。
だとすると、今の時代の雰囲気は作り手にとって望ましい時代だろうか。
はっきりしていることは、天才的個性も時代を超えることは出来ないが、
時代の雰囲気や感性に抗いながら、時代に拮抗できた作品だけが時代を超えて生き続けるのだろう。
↓灰被り蕎麦の壺
前の砧と同じように薪窯に入れた釉薬もの。
薪窯の大きな魅力は、時たまいい作品になるよう窯が助けてくれるところだ。
神も仏もない世の中だが、私の薪窯には小さな「窯の神さま」が時々来るようだ。
何時も御支援を願うのだが、そうそう甘い顔は見せてくれない。