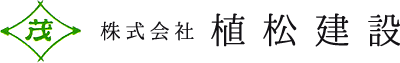物の力、もしくは 物に執して
近代日本文学の中で、夏目漱石と太宰治はよく読まれ続ける双璧といえる。
二人とも文庫本の出版数は断トツの数字だと何かで読んだ記憶がある。
中学生の頃から太宰は好きで、それほど深く理解できたとは思えないがよく読んだし、学生時代にはなけなしの金をはたいて全集も買った。
個人的には、中期安定期の短編が好きで、うまい作品が多いと思う。
太宰は後世の作家や批評家にも多くの影響を与え、各人それぞれの太宰論や比較論を上梓している。
太宰治という作家の全体像を知りたくよく評論にも目を通したが、今もって漠然とした理解しかない。
ただ太宰治の作品は箴言の宝庫で、生きることを考える多くのヒントが無尽蔵にあると思う。
死の想念に憑りつかれた作家の言葉に生きるヒントを見出すこの皮肉!
私が一番好きで影響を受けた言葉。
確か処女作『晩年』にあった一節。
確認するのも煩わしい年齢ゆえ、違っていたら容赦と連絡を。
「死のうと思っていた。今年の正月、よそから着物一反もらった。お年玉としてである。着物の布地は麻であった。
鼠色の細かい縞目が織り込まれていた。これは夏に着る着物であろう。夏まで生きていようと思った。」
この文は、死の想念に憑りつかれながら、必死に生きようとした太宰のアンビバレントな思いなのだろう。
生きる理由をたかが着物一反に託した自殺依存症者(!)のなお生きようとする姿と、侮れない「物の力」への言及がとても気に入っている。
ただし、私の理解はオーソドックスな理解ではないかもしれない。
太宰の生きようとする契機を「物の力」と受け取るのは少しずれているかも知れない。
だが、他人から見たらどうということのない<物>に、私たちは慰藉されたり小さく励まされることがよくある。
これは多分、私のように単純で軽い人間だけの特性でもないだろう。
人間の本質のある部分は、いたって単純で軽いと思うこの頃だ。
「食事を切り詰めても,いいやきものが欲しい」とは、私に「やきもの」の持つ美と感動を教えてくれた人の言葉。
彼はその言葉通り行動し、私は傍から見ていて時に怖くなったことがある。
たぶん<美>の深淵に下りて行こうとしたら、もしくは<美>の神の腕に抱かれようとしたら、
安宅英一(!)を持ち出すまでもなく、どこかで彼らのような軽い狂気や執念が必要であろう。
いっぱしのコレクターを自認できるほど「やきもの」にのめり込んだが、
実のところいい「やきもの」を鑑賞したり、触れているだけで何時間でも過ごせるから不思議だ。
ある時には映画や読書よりも長い時間を充実して過ごせる。
私のこのやきもの(美)に執する姿は、傍から見れば『病膏肓に入る」と映るかもしれないが、
この至福の時を与えてくれる「物の力」は決して小さくない。
だが、いつの時代も良いものほど高い。特に美術品は。
「それにつけても金の欲しさよ」だ。
(自然釉筒)