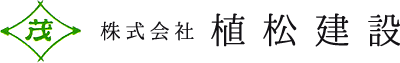<罰>は<罪>を抑止できるか? その3
中世日本において思想や哲学という人間の存在の在り様を問い、解明しようとする思索や行動は、
「宗教」という姿で出現せざるを得なかった。
「思想」や「哲学」という概念自体が社会に存在しなかったからであろうか。
『末法』と言われたこの時代は乱世の常として、誰もがいつも死と隣り合わせで生きていかざるを得なかったから、
民衆が「救い」を求めるとき、宗教が一番大きな救済の役割を演じられたのだろう。
この時代は多くの優れた宗教家を輩出したが、彼らの思想(宗教上の教義)のうち、
そののち普遍性を獲得したものだけが現代まで生き延び、多くは時間の波に洗われて自然淘汰され、
いま多くの宗教的な教義は「儀式」的に残存しているに過ぎない。
歴史を生き延びた彼らの思想は、「仏教の教義」という枠を超え、普遍的思想として今も多くの人々に影響を与えている。
「歎異抄」はその普遍性において他に例を見ないほどよく語られているから、
門外漢の私が語るべき余地はないと思うが、あえて自分の理解のために「第13条」に触れてみたい。
私の記す文章はいつも自分でもくどい部分があると思うが・・・。
『歎異抄』第13条私訳
また、あるとき「唯円房は私の言葉を信じるか」とおおせられたので、「もちろんです」と申し上げた。
「それでは、私のいうことに背かないか」と重ねておおせられたので、謹んで背きませんと申し上げた。
すると、「それでは、ひとを千人殺してみなさい。そうすれば浄土への往生は決定するだろう」とおおせになった。
「おおせではございますが、一人たりとも私の器量では殺せるとは思えません」と申し上げたところ、
「では、どうして私の言葉に背かないと言ったのだ」とおおせになった。
「これでわかっただろう。何事であれ、自分のこころの思うままになるのであれば、浄土に往生するため人を千人殺せと言われれば、
ただちに殺すこともできるだろう。しかし、一人でも殺す『業縁』がないから殺せないないのだ。
私の心が善良だから殺さないのではない。また殺すまいと思っても、百人、千人を殺してしまうこともあるのだ」
とおおせになった。
ここから、親鸞は彼の教義の本質である「願の不思議」という「他力」の深淵に入っていくが、
とりあえずはここまでとする。
いつ読んでも緊張感の漂う文章だ。
この文のキーワードは当然『業縁』になるが、例えばそれは「契機」や「必然性」よりも重い考えであろう。
そして、人が<罪>をおかすのは、あくまで個人の心の中にある善や悪によるのではなく、
その個人を<罪>にいざなう「悪縁」とでもいうべき、時間が積み重なった人間の関係のひずみだとしている。
(これは『業縁』についての私の理解)
だが、私たちは殆ど、<罪>を犯すのはその個人に何らかの原因があり、
個人が内なる「悪の芽」を抑制出来ないから<罪>を犯すと考える。
どうしても私のような「凡夫」の想像力では、
「また、害せじとおもうとも、百人千人をころすこともあるべし」までは到達できない。
せいぜいが、この第13条を「知識」として理解するだけだ。
親鸞は、<罪>の根源的出自はその個人の心の問題ではなく、個人にまとわりつく深い諸関係だと喝破している。
親鸞が「善人往生す、いわんや悪人をや」と『悪人正機説』で語ったその思想の根拠は、
『業縁』によって悪事をなしてしまう人間こそ、浄土で救済される(べき?)と宣言したのではないだろうか。
前回「生まれたばかりの子供に悪の芽はあるか?」と自問した。
乏しい認識ではあるが、
生まれたばかりの子供の中に、「かれの責に属さない悪の芽」はあると思う。
悪の芽が、その後<罪>として出現するか否かは別として、
生まれたばかりの子供の中にも「悪の芽」がある場合があると考えている。
かれの責に帰さない「悪の芽」は生涯にわたって付きまとうものであるが、
人は誰もが持つ「悪の芽」と、生きていく過程でどのように付き合って行かねばならないのだろうか?
続く
(焼き締め瓶)