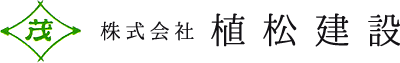雨の訪問者
映画「雨の訪問者」が公開されたのは1970年。
制作が「さらば友よ」のセルジュ・シルベルマン、監督が「禁じられた遊び」、「太陽がいっぱい」のルネ・クレマン、
音楽フランシス・レイ、主演チャールズ・ブロンソンという、
当時人気絶頂のスタッフで作られたミステリー映画で、それだけでも話題になった作品だ。
ラジオを聴きながら受験勉強をしていた私は、テーマ音楽があまりに頻繁に流れるので違和感を持ったほどだった。
映画が興行的に成功したかどうか知らないが、配給会社がここぞと宣伝費をつぎ込んだのだろう。
ほとんど毎日テーマ音楽が流れていたので、今もってその旋律が耳に染みついている。
1970年という年は、私の人生では味気なくストレスに満ち溢れた年だった。
その年の3月に工業高校を卒業し、あらかじめ覚悟はしていた予備校生という身分で上京したが、
容量の少ない頭脳にただ知識という情報を詰め込んで記憶させ、受験という不安に相対していた時期だ。
工業高校では数少ない進学組の友人と、「俺たちは激動の70年浪人組」と粋がって浪人生活に入ったが、
予備校に通ってみれば普通高校の生徒との学力差は歴然で、すぐに劣等感と焦り、不安など思い出してもうんざりする日々が始まった。
そんな時公開されたのが「雨の訪問者」だった。
映画館で見た記憶だけはあるのだが、日比谷だったか渋谷だったか思い出せない。
1970年は、日米安保条約改定の年で巷は騒然としていた時期だったが、
安保粉砕を叫ぶ学生運動も、67,68年の勢いはなく運動が後退局面に入ったように見えた。
またこの年、三島由紀夫が市ヶ谷の陸自駐屯地で割腹自殺をするなど、今思うと日本文化のエポックメイキングの年だった気もする。
予備校の授業について行くのが困難な少年にとっては、光の見えないトンネルの中で不安が充満した毎日を過ごし、
酸素不測の金魚のように呼吸だけして生きていた気がする。
息が詰まる私の1970年を象徴する一つが「雨の訪問者」と言える。
当たり前だが歳月というのは残酷で、シルベルマン、ルネ・クレマン、フランシス・レイ、チャールス・ブロンソン、
そしてこの映画に共演したジル・アイアランド(ブロンソンの妻でセクシーな女優だった)もみんな亡くなり、
ショートカットとそばかすがパリジャンそのままだったヒロイン・メリー役のマルレーヌ・ジョベールも、今どうしているか知らない。
(記憶では、メリーが爪を噛む癖がある女として設定されていた気がするが、
精神的に少し不安定な女をこういう演出で表す丁寧なつくりにしびれたものだ)
「雨の訪問者」も過去のものになり、おそらく再放映されることもないだろうが、今見てもフランス映画らしい粋な雰囲気は十分あると思う。
アメリカ映画のような判り易さがなく、観る側の想像に任せたり、微妙に脈絡を飛ばす、説明のシーンを極力省く等いかにもフランス映画らしい。
当時フランス映画や文学は、人間を描いてはどの国のそれよりも先鋭的だったが、今はどうなのだろう。
私が予備校生活が半年以上たってから、理系コースを文系コースに変えフランス文学を目指したのも、
この時代のフランス映画が醸し出すフランスにあこがれたからだ。
「雨の訪問者」という言葉が浮かんだのは、梅雨入りのころから実家の庭に雨の中に立ち尽くすノラが現れたからだ。
猫は雨に濡れるのを嫌うと思っていたが、このノラは雨を意に介さず濡れながらいつも立っていた。
晴れた日の居場所も庭の日陰で苔が生えた場所に座るから、体を冷やしているのだろうか。
首と右肩に大きな生傷があり、痩せこけて近づくと逃げるという典型的なノラだったが、
その日から私のノラ懐柔作戦が始まり、エサと愛想笑いで手なずけ、ようやくノラも誰が庇護者か認識し始めたのが今日この頃だ。
しょせんノラの知恵よりは人間の方が上手だということ。
雨の中にたたずむノラに出会わなければ、私の人生で一番暗い1年を思い出すこともなかったかもしれないが、
当時を思い出すきっかけを作ったノラに感謝する思いもある。
↓最近は工房前の作品棚が定席の居場所らしい。
エサをあげてもいままでろくに食べてこなくて胃が小さいのか、
他の猫の半分も食べない。
時には雨が差し込むが、こいつはここからあまり動かない。
ノラの特徴で毛並みがガサガサしている。
太らせるのに時間が掛かりそうだが、そのうちびっくりするくらいのデブにしてやるつもり。
ちなみに、以前来ていたミミキレは近所の「猫ボランティア」の家で太って暮らしている。